香田浦残石(三四郎岩)
「史跡 三四郎岩」より
天正11年(1583)から始まった豊臣秀吉の大坂城築城に際し、香川県内各地からも巨石を採取した。この大がかりな採石は詫間でも行われ、香田浦・粟島の福部箱浦海岸などにその形跡が残っている
香田浦の場合、豊後から石工を呼び寄せて採石にあたらせた。この石工の中の一人、三四郎という者が巨石運搬中誤ってその下敷になり即死した、後、村の人はこの石を三四郎岩と呼び、かたわらに祠を建ててその霊を祀った。
この三四郎岩は、長さ5m、幅2m、高さ(地表に出ている部分だけで)1mの巨石である。
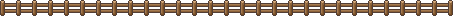
【管理人の鑑識モード】
秀吉の大坂城築城に伴う巨石というのは本当であろうか?大坂城本丸地下の石垣石材や三の丸の石垣といった伝秀吉時代の石垣は自然石系が多く矢穴の跡が残る割石は少ない感じがします。しかし、この三四郎岩は矢穴が多く残っている点から少なくとも秀吉時代のものの可能性は低いと考えます。
また、上記説明の中にある「豊後の石工を呼び寄せ」というところが本当の話であったとしたら、むしろ元和以降の大坂城助役に伴う、豊後系大名の採石地が香田浦であって、運び出しを中断した石材という見方の方が自然な感じがします。
 |
 |
上:三四郎岩長辺側面
左:三四郎岩海側面
※共に合成写真のため多少の歪みがあると思います。 |
 |
三四郎岩山側面
切り出し途中で放棄のためか、石材の形が整っていないのが特徴 |
 |
矢穴跡
上場長10cm、「U」形の矢穴跡 |
 |
石材二次加工用の矢穴?
上場長は10cm |
|