紀伊国分寺 跡
所在地:和歌山県
那賀郡岩出町西国分 |
 |
【歴史】
『紀伊国分寺講堂跡』説明板より
現在建っているいるのは町指定文化財の本堂で、江戸時代元禄年間につくられたものですが、その下には奈良時代紀伊国分寺講堂の基礎である「基壇」が復原されています。
発掘調査の結果、奈良時代の講堂は、東西27m、南北14mの大きさの建物と推定され、元慶3(879)年の紀伊国分寺焼失後も、中世以降は同じ場所に数回にわたって御堂が建て替えられ、今日まで国分寺の法灯が伝えられてきたことがわかりました。
『紀伊国分寺塔跡』説明板より
塔の基礎にあたる「基壇」と呼ばれるもので、一辺が16mの正方形をしており、高さは1.2mあります。
土や砂を突き固めて重ねていく「版築」技法で築かれ、周囲に平瓦を積み上げた「瓦積基壇」という種類のものです。基壇の中央には、塔の芯柱を据えた大きな礎石があり、その周囲に計16個の礎石があります。塔は、礎石の配置から見ると、初層部分の柱間が9.3mで、高さ50mに達する七重塔でであったと推測できます。これらの礎石やガラス越しに見える瓦積基壇はすべて奈良時代そのままのものです。
|
 |
 |
 |
| (写真1) |
(写真2) |
(写真3) |
 |
 |
 |
| (写真4) |
(写真5) |
(写真6) |
 |
 |
 |
| (写真7) |
(写真8) |
(写真9) |
|
【雑記】
紀伊国分寺の跡をじっくり見て廻ったのは小学校の遠足以来で、前回塔基壇の現説の際は現説以外の所は見ませんでした。整備が行き届いている!。
現状は建物が残る講堂基壇(写真5奥)、金堂基壇(写真5手前)、塔基壇(写真1・2)、鐘楼基壇(写真6)、経蔵基壇、僧房基壇(写真7)が瓦で基壇が整備され、僧房基壇上には柱をイメージしたものがつくられています。寺の周囲を廻っていた廻廊基壇、中門基壇(写真4)、南門基壇(写真3)は土盛りに芝生をはって整備されています。
国分寺跡南側に隣接して資料館がありますのでセットで廻るとより面白いでしょう。車利用の場合ですと資料館の前と農免道路脇に駐車スペースがあります。
参考までに写真8・9は塔基壇の発掘現説の時の写真ですが、塔の礎石上に突起が見られますが、現状では見ることができません。(ひょっとして逆さまにして復元?)瓦基壇も平瓦の積み上げのイメージになってしまいますが、軒瓦も角部では使用しています。
|
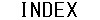 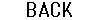 |