平池古墳群
所在地:和歌山県
紀の川市貴志川町神戸 |
 |
【歴史】
『平池古墳群』説明板より
古墳とは、今から1800〜1400年前(3世紀から7世紀)にかけて、土を大きく盛り上げ造られた有力者の墓です。
平池古墳群は、紀の川市貴志川町神戸の平池内にあります。最初から池の中にあったのでなく、古墳が造られたからずいぶん後に池が造られたものです。貴志川流域には古墳がたくさん造られ・「紀州の飛鳥」と呼ばれています。
「平池1号墳」(説明板より)
現在の平池北岸に位置し、長さ31.5mの前方方円墳と考えられます。古墳はかなり削られていたため変形し、遺体を納めた主体部も発見できませんでした。土を掘って調べた【発掘調査】結果、古墳の周りには幅1mほどの溝【周溝】がめぐらさせ、さらに東側中央で途切れ、出入口となっていたこと【陸橋】が判明しました。
出土物としては、円筒形や器財形をした埴輪のほか、須恵器の高坏・甕が見つかっています。
これらのことから、1号墳は古墳時代後期(6世紀中頃、今から1500年前)に造られ、当時の貴志川流域で力を持っていた首長の墓と考えらます。
「平池2号墳」(説明板より)
平池西側に位置し、現在池の中に島のような形で遠望できます。古墳はやや南北の長い楕円形で、長径31.5m、短径28mの円墳と考えられますが、削られて変形しています。古墳の頂上【墳頂部】付近に、横から出入りできる遺体をおさめた石の部屋【横穴式石室】の一部がみられ、石室入口は南西部であったことが判りました。1号墳と同じように、古墳の周りには幅2mほどの周溝がめぐらされ、また南西部には溝を掘り残すように造られた陸橋が確認されました。
出土遺物としては、須恵器の坏身・坏蓋・石棺蓋が見つかりました。埴輪はありませんでした。これらのことから、2号墳は古墳時代後期(6世紀末、今から1400年前)に造られ、1号墳と同じように周溝と陸橋を備えた首長の墓と考えられます。
また、古墳の西方から国府型ナイフ型石器やサヌカイトの細石刃等が採取されました。これは旧石器時代を代表するもので、今から約2万年前のものです。
「平池3号墳」(説明板より)
平池南岸に位置し、発掘調査の結果、直径17mの円墳と考えられます。1・2号墳と同じように古墳をめぐる溝を確認しましたが、大変浅くはっきりしません。
古墳からは遺物が見つかりませんでしたが、古墳の高さや形などから、埴輪や須恵器が出てくる前の時期、古墳時代中期(5世紀末、今から1550年前)のものとも考えられます。
|
| 1号墳 |
|
|
|
 |
 |
|
(写真1) |
(写真2) |
|
|
|
| 2号墳 |
|
|
|
 |
|
|
(写真3) |
|
|
|
|
| 3号墳 |
|
|
|
 |
 |
|
(写真4) |
(写真5) |
|
【雑記】
以前職場の方とブラックバスを釣りに行って、古墳があることが判った所。長い間再訪と思いながら訪れる機会がなく、やっと訪れました。
池の中の円墳のみのイメージでしたが、前方後円墳もあったとは・・・。
でも、池の護岸改修で以前のイメージが全くないです。公園化はええことやと思いますが、史跡保護ではどうなんでしょう?
|
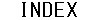 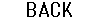 |